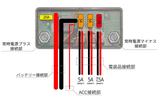まとめ:RIDE編集部
ヤマハ「YZF-R7」1999年
![画像: YAMAHA YZF-R7[OW02] 1999年2月 総排気量:749cc エンジン形式:水冷4ストDOHC5バルブ並列4気筒 海外向けモデル:約400万円](https://d1uzk9o9cg136f.cloudfront.net/f/16782548/rc/2022/06/08/197149db4b16c11376816e82b2d3a30d6a17f076_xlarge.jpg)
YAMAHA YZF-R7[OW02]
総排気量:749cc
エンジン形式:水冷4ストDOHC5バルブ並列4気筒
海外向けモデル:約400万円
新型とは違う究極のレースベース、最後を飾る750スーパーバイク
OW01、YZF750SPと続いたヤマハのスーパーバイクレース用のベースモデル。その最後を飾るモデルとして1999年に発売されたYZF-R7。1998年にデビューしたYZF-R1に連なるYZF-Rシリーズの1台だ。現行車にあるYZF-R7とは血統が大きく違う。
鍛造ピストンにスリーブレスシリンダー、チタンバルブ、チタン削り出しコンロッドを採用してレース用チューニングに備え、バックトルクリミッターまで装備されたエンジンは、R1と同じくクランク、カウンター、ドライブの三軸配置をコンパクトな三角形にすることで前後長を短縮。コンパクトな車体ながらスイングアームを長く取ることが可能になり、軽快でコントロールしやすい操縦性と優れたトラクション性能がもたらされた。
フレームはR1同様のデルタボックス2と呼ばれるアルミ製ツインスパーフレーム。ステアリングステムからスイングアームピボットを直線的に繋いでR1の2倍近い高剛性を備える。サスは前後共にオーリンズ製フルアジャスタブル。クイックファスナーを多用したカウル、アルミ製燃料タンクなど贅沢な造りだったため、当時日本円で400万円以上という破格の価格設定となった。
ホンダ「VFR750R」1987年
![画像: Honda VFR750R [RC30] 1987年8月31日 総排気量:748cc エンジン形式:水冷4ストDOHC4バルブV型4気筒 新車当時価格:148万円](https://d1uzk9o9cg136f.cloudfront.net/f/16782548/rc/2022/06/08/d7b5af2a0668caa8316bd3b90f67e298ec7d3fca_xlarge.jpg)
Honda VFR750R [RC30]
1987年8月31日
総排気量:748cc
エンジン形式:水冷4ストDOHC4バルブV型4気筒
新車当時価格:148万円
限りなくワークスレーサーに近い存在、35年を経た今でも色褪せない個性的なデザインと技術力
1980年代半ばの鈴鹿8耐で圧倒的な強さを誇っていたマシンが、ホンダのワークスTT-Fマシン・RVF750だった。
独特のサウンドを放つ強力なV4エンジンをコンパクトなボディに積んだRVFは、8耐で育ち世界GPでその名を轟かせつつあったW・ガードナーの豪快なライディングによって1985年・1986年と8耐を連覇。V4マシン・RVFの戦闘力の高さを見せつけたが、この当時RVFのベースとなったVFRシリーズには純スーパースポーツは存在しなかったのだ。当然のように、世界中のライダーはRVF直系のスーパースポーツを待望した。
そんな声に応え1987年に姿を現したのがVFR750Rだ。形式名「RC30」と呼ばれることが多いこのモデル、何から何まで特別だった。そもそもRC30はプライベーター向けのレースベース車両として開発された。そう、レプリカではなく、ある意味本物のレーサーなのだ。だからこそ最強マシンであるRVFで得られたノウハウが惜しみなく注ぎこまれた。

VFR系のV4エンジンは2本リングの専用ピストン、チタンコンロッドなどレーサーそのもののパーツを使い、レースで使うことを前提に大幅リファイン。さらに剛性の高いフレームやディメンションももRVF直系、8耐でタイヤ交換を短縮するために採用された片持ちのプロアームもRVFそのもの。全身に及ぶこだわりは世界の度肝を抜いた。
当然価格も平均的な750ccマシンの約2倍、当時市販車最高の148万円で、国内1000台の限定販売。ところが3000台を超える購入申し込みが殺到し、抽選が行われるほどの大人気に。レース用だけでなく、多くの一般ライダーがRC30の「本物」なところにノックアウトされたというわけだ。だからこそ発売から35年を経た現在まで、愛され続けるモデル足りえているのだろう。
スズキ「GSX-R750R」1986年

SUZUKI GSX-R750R
1986年2月
総排気量:749cc
エンジン形式:油冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒
新車当時価格:105万円
初めて100万円を超えた国産車、市販車初の乾式クラッチモデル
1985年3月にSACSを初採用した油冷エンジンを搭載したGSX-R750がデビュー。77馬力のハイパワーに乾燥重量179kgという軽量の組み合わせでユーザーの心を掴み、その3月~12月の販売台数5784台と国内二輪750ccクラスでベストセラーとなった。
その翌年、ルマン24時間耐久レース優勝や、全日本選手権F1クラスチャンピオンなど、輝かしい実績を記念し、GSX-R750のレース仕様車の先進技術を盛り込んだGSX-R750Rが500台限定で発売された。

ヨシムラカラーの外観やFRP製テールカウル一体型シートだけをとっても、見た目の完成度の高いレプリカだったが、実は中身もしっかりと特別仕様となっていた。
ステアリングダンパーや専用ホイール、ラジアルタイヤなどの他、フロントサスペンションに電子制御式アンチノーズダイブシステム「NEAS」を採用。リアにはタンク別体式ショップを搭載した。
市販車としては初となる乾式クラッチや、淡黄色ハロゲンバルブも採用し、その上、国産市販車初の車両価格100万円の大台を超えたバイクとしても話題となったスペシャルな一台だ。