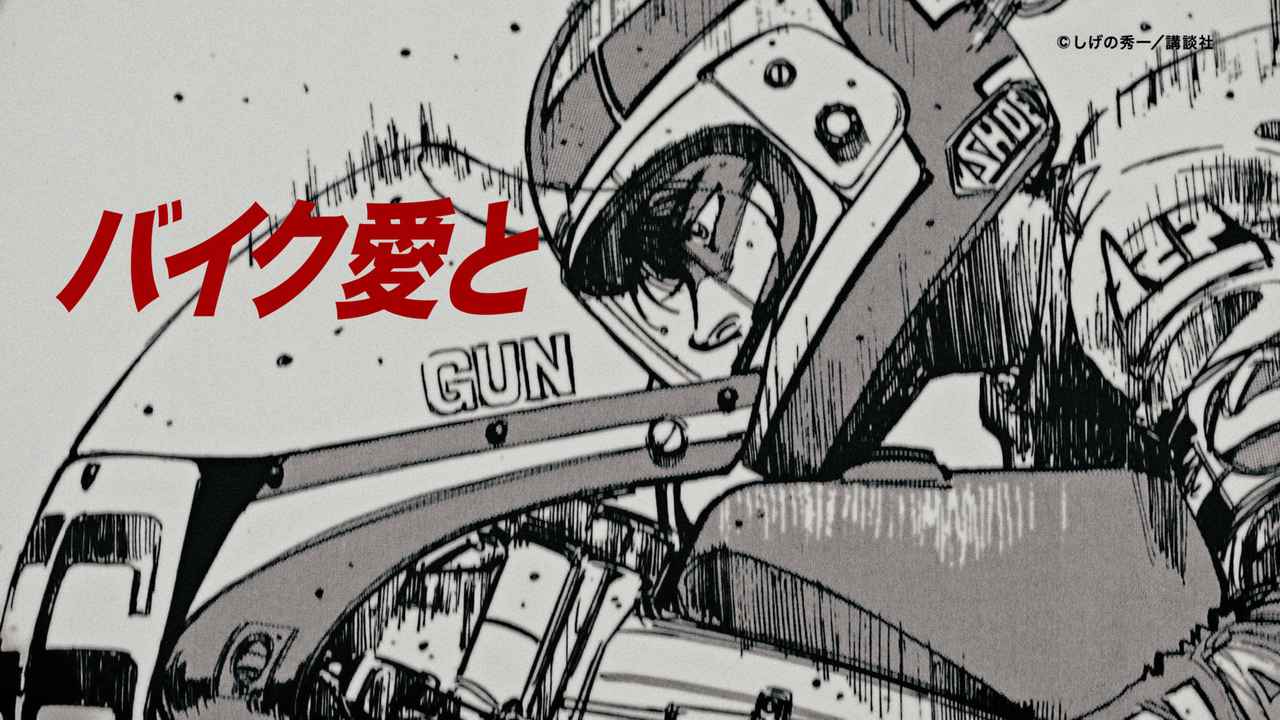まとめ:webオートバイ編集部
あえてアナログな手法とリアルなサウンドにこだわって生まれた“リアル感”
バイク愛と 買取 サービス 篇
www.youtube.comCMを見た多くのライダーが驚いたのが、静止画であるはずの巨摩郡が、まるで本当に走っているかのように振動し、躍動している点だ。
実はこれ、CGによるアニメーションではない。「バイク特有の『G(重力・加速感)』を感じさせたかった」と松井氏は語る 。
そこで採用されたのが、驚くべきアナログな手法だった。同じ絵を何十枚も巨大なドラムに貼り付け、それを回転させて撮影したのだ 。ちなみにこれは、制作を担当した監督からの強い要望だったという。制作スタッフもバイクを愛するライダーだったことから生まれた手法だったのだ。
「カメラのシャッタースピードが追いつかない『ズレ』を利用して、リアルなバイクの振動を表現しました」
デジタル全盛の時代に、あえてアナログな手法でリアリティを追求する。その姿勢こそが、今回のCMの「熱量」を生み出しているのだ。
そしてもうひとつ、さらに驚くべきエピソードがある。それは「サウンド」。
このCMには実車を使った吸気音、排気音がリアルに入れられているが、実はこのサウンドはCMの納品ギリギリのタイミングで収録されたもので、試写の段階までバイクのサウンドは入っていなかったのだという。
通常なら間に合わないタイミング。しかし「バイクの音がない」と澤氏は首を縦に振らなかったのだ。その時のエピソードをこう披露してくれた。
「なんでバイクの音が入ってないの? ということで、間に合いません、というのを間に合わせてもらいました。最終的には『バイク愛、だろ?』という言葉で押し通しました(笑)」
そこから急遽、実車のCB750F、RZV500を手配し、サウンドの収録が行われた。協力したのは、なんとレーシングライダーの加賀山就臣氏。収録の現場でも「澤さんがバイク好きなのが嬉しい」と喜んでくれたという。
時代は変わっても、バイクに対する「愛とワクワク」は変わらない
バイク愛と 販売 篇
www.youtube.com80年代のレースシーンを知り尽くす宮城光氏は、このCMを見た感想をこう語った。
「マシンの描写やバンク角、目線といったリアリティがどう仕上がっているのか気になっていましたが、しげのさんの作品はそこを非常に丁寧に描いている。見ていて高揚感を感じます」
『バリバリ伝説』の連載が始まったのは1983年。宮城氏は、当時と現代のライダーの違いについても言及する。
「僕らの時代は、オートバイと言う乗り物は刺激的に速く走るためのツールだった。少しでも速く目的地に着くためにすり抜けをしたり、ちょっと乱暴な乗り方をしていた部分もありました。でも、今の若いライダーは、渋滞でもちゃんと車の後ろについて走っている。人や社会に対するアプローチが全く変わってきています」
マナーは向上し、楽しみ方も多様化した。しかし、変わらないものもある。澤氏はこんなエピソードも披露してくれた。
「オートバイに縁のなかった新入社員に、実際にバイクを見せ、エンジンをかけると、目がキラキラと輝くんです。こういう機会を作っていくのが我々の使命なんだな、と改めて思います」
宮城氏もこれに同意する。

「最初にバイクにまたがって、エンジンをかけた時の感動。これは全ライダーが共通して持っている原体験です。こうした感動を伝えていきたいですね」
座談会の終盤、話題は「なぜバイク王がこのCMを作る必要があったのか」という核心に迫った。
宮城氏は、バイク王に対して「日本の『第5のメーカー』になってほしい」という期待を寄せる 。
「日本には優秀な4大メーカーがありますが、メーカーだからこそできないこともあります。特定のメーカーに縛られず、バイクのある文化を発信して欲しい。それはバイク王だからこそできる役割なのではないでしょうか」
澤CEOもその想いは同じだ。
「バイクに乗ることで、私の人生はとても豊かなものになりました。バイク王として、と言うより、バイク業界として、マスメディアでバイクのCMを流し続けることが大事だと思っています。業界をもっと盛り上げて『恩返し』をしたい。メーカーさんのCMが減っている今こそ、我々がバイクの火を絶やさず、バイクをもっと知っていただき、ワクワク感を伝えていきたい」
中古車買取・販売店という枠を超え、ライダーの人生を豊かにする「ライフスタイル・カンパニー」へ。そして、バイク文化を次世代へと繋ぐ「ハブ」へ。『バリバリ伝説』の巨摩郡がサーキットで見せたあの情熱的な走りのように、バイク王もまた、新たなステージへとアクセルを開け始めたようだ。